「絵心」という言葉はよく聞きますが、その意味が曖昧なまま使われることが多い言葉です。私は物心つく前から描くことが日常にあったため、「絵心がある・ない」という区別に違和感があります。そこで今回は、美術教育の観点と心理学の観点から、「絵心」の正体を整理してみます。
美術教育的な「絵心」視覚の捉え方そのもの
美術教育では、絵心は「技術の上手い・下手」ではなく、「世界をどのように視覚的に理解しているか」という視点で扱われます。
●絵心がある人の視覚特性
・形を「記号」ではなく「構造」で見る
・光、影、奥行き、リズムなどの視覚情報を敏感に拾う
・特徴を抽出し、線で再構成することが自然にできる
・「比率」「方向」「流れ」などを直感的にとらえる
一言でいえば、ものの見え方が“立体的で、構造的”なのです。
逆に「絵心がない」と言われる場合、多くは
・家=四角+三角
・顔=丸+点+線
といった「記号的な見え方」が強い状態を指します。
これは才能よりも、視覚の注意の向き方の問題です。描く経験が少ないと、記号で処理する習慣が残るため、「絵心がない」と誤解されることが多いのです。
心理学的な「絵心」内側から湧く「表現衝動」
心理学では、絵心は“表現欲求の有無”として語られることがあります。つまり、「描きたい」という内的衝動があるかどうかです。
●絵心がある人の心理的特徴
・感情や思考がビジュアルで立ち上がる
・言語より線や形のほうが整理しやすい
・感動や違和感がそのまま手の動きにつながる
・描く行為そのものがストレス解消や調整になっている
このように、絵心とは「感性の働く方向性」です。視覚で世界を理解し、線や形で外に出すチャンネルが強い人は、自然と“絵心がある”と見なされます。
逆に、「絵心がない」と言われる人は表現衝動が弱いというよりは、
・視覚より言語情報で世界を整理している
・描く行為に興味が向きにくい
・美術的な感情が形として結びつきにくい
という傾向があるだけです。
どちらが優れているという話ではなく、認知のスタイルの違いです。
MADARAが考える「絵心」とは
私にとって絵心とは、「世界の見え方と、内側からの衝動が一致して生まれるもの」です。
・ものの形や光の流れが自然に気になる
・感情の揺れが線になる
・描かずにいられない瞬間がある
・言葉の前にイメージが立ち上がる
これは訓練というより、生き方そのものに近いものでした。
ただし、絵心は生まれつき固定されるものではありません。描く経験を重ねることで、誰でも“視点”と「感性のチャンネル」は変わります。大人になってから急に絵心が芽生える人も多く、美術教育の現場でもよく見られます。
結論:絵心とは「視点」と「衝動」
絵心とは、
・世界の見え方(視覚の取り込み方)
・表現したい衝動(心理的エネルギー)
この2つが組み合わさった状態です。
上手い/下手とは別の話であり、練習すれば自然と育つ“感性の回路”のようなものです。
そして、美術や書道の領域では、絵心は「技術の前にある最も重要な土台」と言えます。
描きたい、伝えたい、形にしたい。その気持ちが動き出した時、絵心はすでに芽生えています。


-
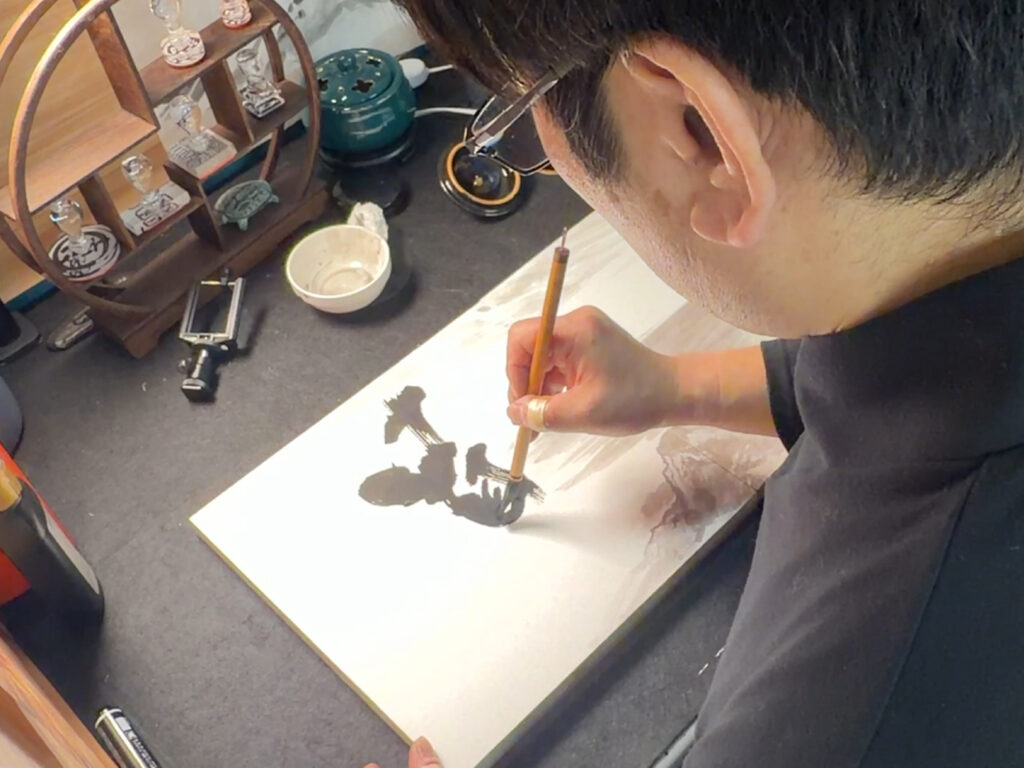
毎朝のルーティン
-
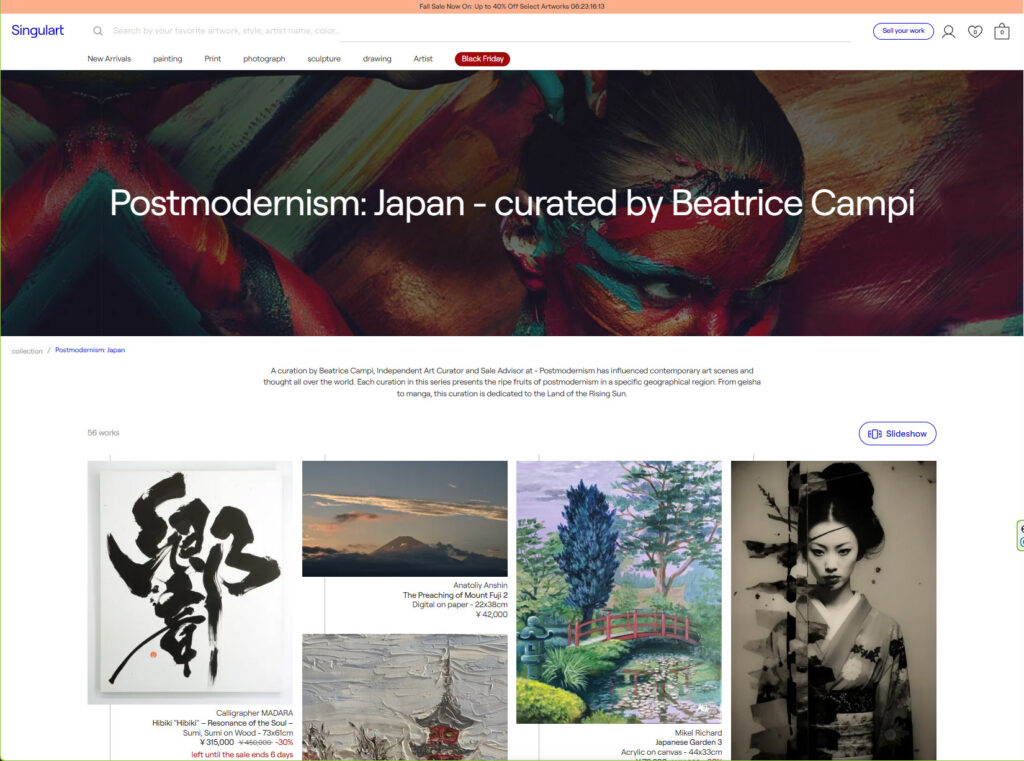
海外キュレーターによる特集『Postmodernism: Japan』に、斑(MADARA)の作品が選出されました
-

英語名を美しい漢字に変換する方法
-

東京のホテルで「カスタム書道作品」を受け取る方法
-

ドキュメンタリー映画の撮影が無事に終了しました
-

筆跡術を動画で解説
-
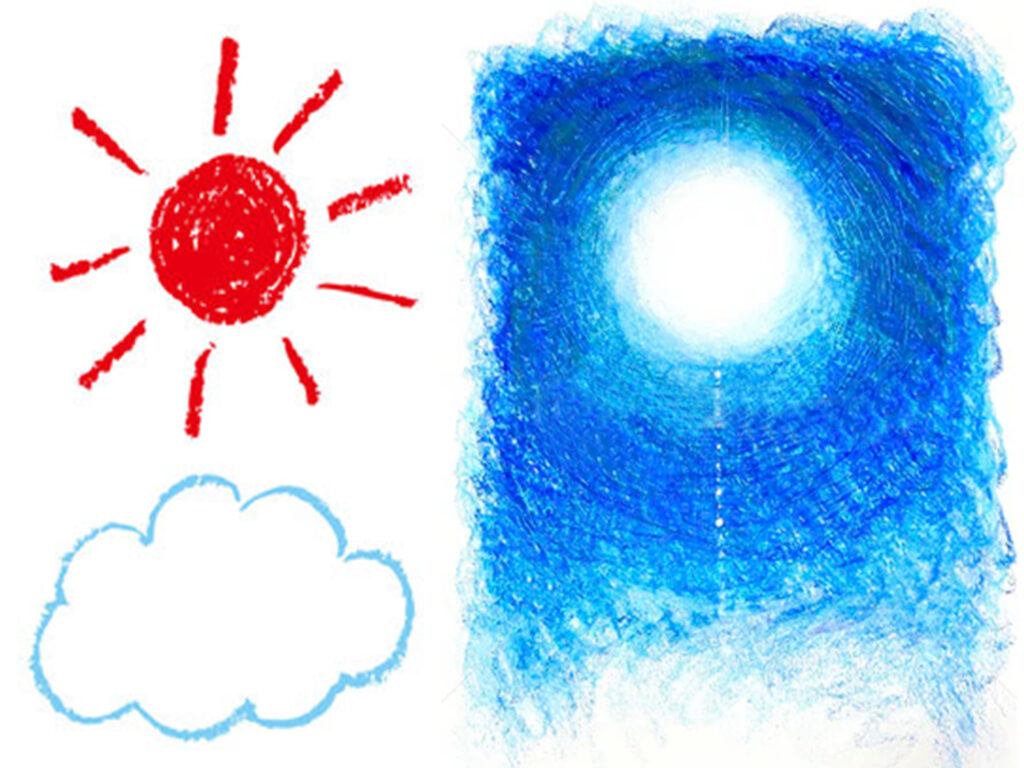
幼稚園の頃から感じていた違和感「赤い丸の太陽」が教えてくれた、私の絵心の正体
-

絵心とは何か? 美術教育と心理学の視点から見た「描く力」の正体
-

作品制作記録:「祈 ― 湘南平塚の海にて」



